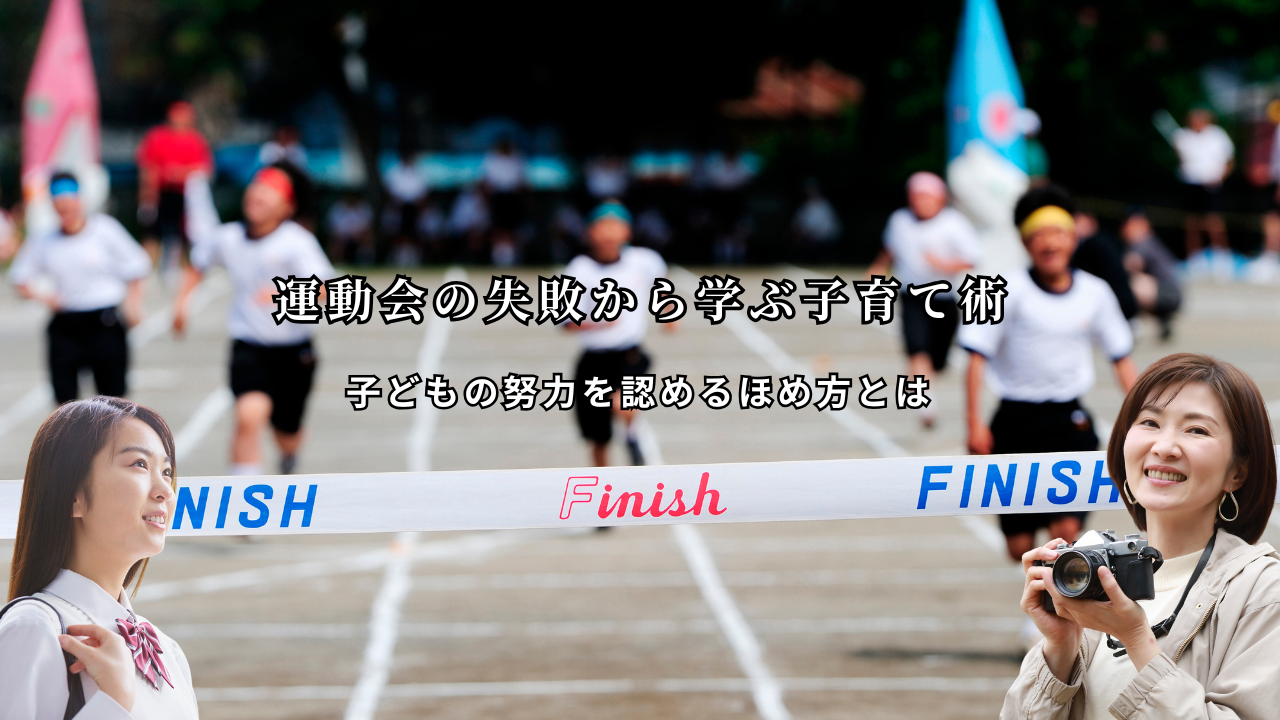運動会シーズンになると、朝からお弁当を準備し、校門に並んで席を確保するご家庭も多いですよね。
我が家もそのひとつ。子どもの徒競走があると聞いて、応援のスイッチが一気に入りました。
「がんばれ!」「あと少し!」
そう声をかけながら必死に応援していました。
ところがゴール直前で子どもが転んでしまい、惜しくも順位を逃してしまったのです。
思わず胸がぎゅっと締め付けられる瞬間でした。
思わず口から出てしまった言葉
本当は「よく頑張ったね」と抱きしめてあげたかった。
でも、私の口から出てしまったのは――
「もう少しだったのに!いつも最後でうまくいかないのよね、あなたは」
子どもは無言で自分の席に戻り、夫からは「どうしてあんな言い方をするんだよ」と責められました。
なぜこんな言葉が出てしまうのか。
それは、私自身が子どもの頃に「褒められた経験が少なかった」からだと思います。
褒められた経験が少ないと起きやすいこと
褒めてもらった経験が少ないと、どうしても「できなかったこと」「失敗したこと」に目が行ってしまいます。
そして、本当は言わなくてもいいひと言を、つい口にしてしまうのです。
たとえば、こんな場面もありました。
・テストで80点をとった子どもに「あと20点で100点だったのに」と言ってしまう。
・習い事の発表会で少し間違えただけなのに「やっぱり練習不足ね」と口にしてしまう。
心の中では「よく頑張った」と思っているのに、つい結果ばかりを見てしまう…。
これでは子どもは「自分は認められていない」と感じてしまいます。
だからこそ、日頃から意識して
「悪いところではなく、良いところに目を向ける」練習が大切なのです。
言い直せた、もうひとつの声かけ
運動会が終わって家に帰ったあと、私は改めて子どもに声をかけました。
「今日は本当に頑張ったね。お疲れさま」
すると子どもが驚いた顔で言いました。
「ママ怒ってないの?だって一位じゃなかったんだよ」
私はこう答えました。
「一番じゃなかったけど、最後まで走り切った努力をママはちゃんと見ていたよ。
ママにとっては一番なんだよ」
そのときの子どものほっとした笑顔は、今でも忘れられません。
努力を認めることが子どもの力になる
結果が伴わなくても、努力を認めてもらえることは子どもの心に大きな安心を与えます。
別の日のこと。
子どもが苦手な鉄棒の逆上がりに挑戦していました。
何度やってもできなくて、泣きそうになっていたとき、私は「できないね」と言いかけましたが、ぐっとこらえてこう言いました。
「何度も挑戦しているのがすごいよ。諦めないところが一番いいね」
するとその日、逆上がりはできなかったけれど、子どもの顔には満足そうな笑みが浮かびました。
努力を見てもらえている――それだけで挑戦する勇気が湧くのです。
親の言葉は子どもの未来をつくる
親のひとことは、子どもの自己肯定感に直結します。
「なんでできないの?」と責めれば、自信を失う。
「よく頑張ったね」と認めれば、「次も頑張ろう」と挑戦できる。
運動会や日常の小さな出来事は、子どもにとって「自分がどう見られているか」を実感する大切な場面です。
だからこそ、努力を認める声かけが必要なのです。
まとめ
運動会での転倒という「失敗」に見える出来事も、親子にとっては大切な学びの場でした。
・結果よりも努力を認める
・できなかったことではなく、できたことに目を向ける
・「頑張ったね」のひと言を忘れない
この積み重ねが、子どもの自己肯定感を育み、未来への力になります。
今日から少しだけ意識して、子どもにかける言葉を変えてみませんか?